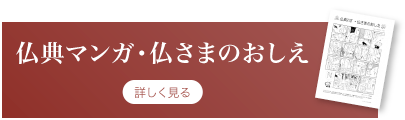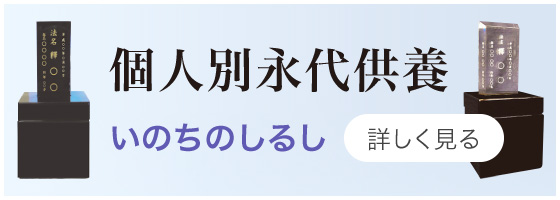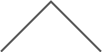今日は報恩講の「報恩」という言葉について考えます。この言葉は宗祖親鸞聖人の三十三回忌より意識されるようになりました。覚如は聖人三十三回忌のときに報恩講式という聖人の徳を称える文を作られました。これは聖人のことを後世に伝えるために作られた文です。また、蓮如上人は御文の中で、何度も「報恩講」という言葉を使われています。もともと「報恩講」という言葉は親鸞聖人のことで使われていたわけではなく、当時は他宗でも使われていました。蓮如上人が何度も使われたことにより世の中に広まり、浄土真宗固有のことばとして使われるようになりました。地方によっては「御取越」という言葉が使われることもあります。報恩という言葉の語源はお釈迦様のおられたインドのサンスクリット語の「クリタジュニャター」という言葉です。
お釈迦様の教えがインドから中国に伝わって漢文に翻訳され、日本に伝わりました。ただ、同じインドのお経を翻訳したものでも、翻訳した人によって解釈の差異があるため、漢文による表記の違いが何種類もありました。また、翻訳せずにインドの言葉の読み方を採用して当て字として漢字を使用する場合もありました。「南無」は「ナマス」という言葉で意味は「心から信ずる」ということで、「阿弥陀」は「アミターバ」「アミターユス」というインドの言葉を漢字にしたものであり、「ブッタ」というインドの言葉は「覚った者」という意味を持ったものです。親鸞聖人の書かれた教行信証には「「信」はすなはちこれ真なり、実なり、誠なり・・・」とあり、「信」という言葉の意味について様々なお考えを明らかにされました。
先ほど紹介したサンスクリット語の「クリタジュニャター」ですが「クリタ」は「為される」という意味で、「ジュニャター」とは「知る」「悟る」という意味ですから、「なされたことを知る」という意味です。親鸞聖人は「報徳」という言葉を単独で使用するよりも「知恩報徳」という言葉で度々使用しています。「知恩」の字は分解して解釈すると「原因を知る心」となります。「報恩」だと少しニュアンスが違います。七高僧をはじめとした過去の人たちが「知恩報徳」を大事にされていたのでそこから二文字をとって「報恩講」と呼ばれるようになったものと思います。他にも同意の語として「報恩謝德」という言葉も親鸞聖人や蓮如上人は使われました。
龍樹は大乗仏教の祖と言われます。「大乗仏教」は皆共に救われる教えを説く仏教です。主著「大智度論」には「恩の重きを知るがゆえに常に仏を念ず」「恩を知るがゆえに広く供養す」といずれも「恩を知る」と記されてあります。天親は「浄土論」を著し、曇鸞はその注釈書の「浄土論註」を著しました。これには「恩を知りて徳を報ず」と記されています。ここでも「知恩」と「報徳」の関係に言及しています。これによってインドから中国へ浄土教の教えがしっかりと伝えられました。
道綽は曇鸞の石碑にひどく感銘を受けたそうです。その弟子の善導は「往生礼讃」を著し、その中で「大悲伝普化 真成報仏恩」と説かれました。これを受けて親鸞聖人は教行信証の中で「仏恩の深遠なるを信知して正信念仏偈を作る」と記されています。「仏恩」を「信知」して正信偈を作られたことがわかります。「恩を知る」ということが行動を起こす一つの縁となっています。
ボランティア活動で有名な尾畠春夫さんは「かけた情けは水に流せ、受けた恩は石に刻め」と言われました。私たちは反対のことをしがちです。経済的には大きく発展しましたが、他人への感謝やつながり、いのちへの敬愛の念が希薄になっている私たちは幸せでしょうか。私たちの暮らしは豊かになっていますが、幸せになっているでしょうか。
神戸にレインボーハウスという阪神淡路大震災遺児のケアセンターがあります。1999年に使用開始されました。初代館長の林田さんは東北の震災の被災地に施設建設のため東北事務所長として赴任しました。その際阪神大震災の遺児が東北の震災の被災地活動に従事していることを心強く思い、大変喜ばれていました。阪神の震災を経験した遺児たちだからこそ我がこととして受け止め、被災地の人たちに優しく接することができました。受けた恩は与えた人に対して直接お返しすることはできないかもしれませんが、違う形でお返しすることができます。「知恩報徳」恩を知り感謝の気持ちを返すという一つのかたちであると思います。
一念多念文意に「もとめざるに無上の功徳をえしめ、しらざるに広大の利益をうるなり」と記してあります。私たちは求めたわけではないのに、知らないうちにいのちを与えられて暮らすことができています。様々なご縁によって生かされてきたことが知られます。それを知ると、周りに振り分けずにはいられません。共に幸せでなければ自分の幸せにはなりません。本当の幸せとは皆共にそうであることであり、それを表すことばが「知恩報徳」です。