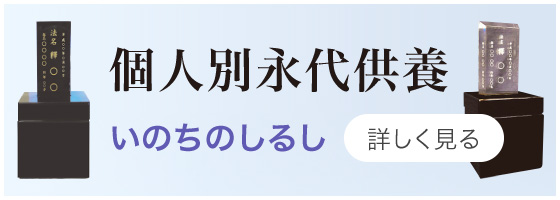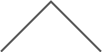本日は「報恩のめざめ」という講題でお話をさせていただきます。「知恩」とは「為されたことを知る」ということです。してもらったことを知るということはなかなか難しいことですが、それを「知恩」と言います。これを知らなければ自分の思いばかりを振り回して、周りが見えなくなってしまいます。恩を知れば、「報徳」つまり何かをせずにはおられなくなります。これは頭でわかるということではなく、自分の身で感じるという心が自ずと生じてきます。親鸞聖人の生涯は「知恩報徳」の生涯でした。没落貴族の子息であった親鸞聖人は比叡山に九歳のときに入り、20年にわたって修行をしましたが、そこで救われることはありませんでした。比叡山を降りて聖徳太子の祀られている六角堂に籠りました。そこでの夢のお告げに従って、法然上人の門下に入りました。「ただ念仏して」こそ仏に助けられるという法然上人の仰せに従って6年間念仏の教えを受けました。35歳で念仏の弾圧を受け、流罪となりました。『御伝鈔』にはその時親鸞聖人が「もしわれ配所におもむかずば、何によりてか辺鄙の群類を化せん。これ猶師教の恩致なり」と言われたと記されています。「師教の恩致」とは師の教えのご恩という意味です。つまり、このことがご縁となって越後の人々に念仏の教えを弘めることができた、そのことこそ師のおかげであるということです。
『 あたりまえ 』
あたりまえ
こんなすばらしい事をみんなはなぜよろこばないのでしょう
あたりまえであることを
お父さんがいる お母さんがいる 手が二本あって足が二本ある
行きたいところには自分で歩いてゆける 手をのばせばなんでもとれる
音が聞こえて声がでる
こんなしあわせはあるでしょうか
しかし、だれもそれをよろこばない あたりまえだ、と笑ってすます
食事がたべられる
夜になるとちゃんと眠れ、そして又朝が来る 空気をむねいっぱいにすえる
笑える、泣ける、叫ぶこともできる 走りまわれる
みんなあたりまえのこと
こんなにすばらしいことを、みんなは決してよろこばない
そのありがたさを知っているのは、それを失くした人たちだけ
なぜでしょう
あたりまえ
この詩を書かれたのは井村和清さんというお医者さんです。30歳の頃に膝に悪性腫瘍がみつかり、膝から下を切断しました。義足をつけて勤務を続けましたが、事情によって退職することとなり、皆さんに挨拶をされました。そのときに悲しい3つのこととして ①患者さんを診てもどうしても治せない患者さんがいることの悲しさ ②経済的に困っている患者さんが存在すること ③患者さんの気持ちになってあげることのできない悲しさ を挙げられました。その中で③番目の悲しさが特につらいことです。誰かが私を心配してくれると、私たちは生きていくことができます。阿弥陀様は「同悲同苦」といって、私たちに寄り添って悲しみと苦しみを共有してくださる「同体の大悲」である存在です。
井村さんが医者であるとともに患者であるという立場から著した本があります。『飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ』という本です。井村さんはこの本が出版される前に亡くなられました。飛鳥とは長女の名前で、亡くなられた時に、奥さんのおなかのなかに二女がおられました。この本は二人の子供たちへの思いを綴られたものです。この本の中に、「目に見えるものだけが全てではなく、目に見えないものこそがずっと残るものであり、それこそが大切なものです」と記してあります。亡くなった人は目には見えませんが、私たちに色々なはたらきをなさっています。亡き人を案じる私たちは亡き人から案じられています。
真宗とは「真実を宗とする」という意味で、「宗」とは「要」ということです。真実は目に見えませんが、大きなはたらきをしています。亡き人は大きなはたらきを以て、私たちを見守っています。このはたらきを「念力」とか「願力」といいます。親は死んでも願いは残ります。そして、仏さまの願いである本願に目覚めさせてもらうことが大切なことです。
井村さんは亡くなる前にご両親にお礼を言うために富山に帰省しました。生きている内に親に対してお礼をいうことはなかなかできません。親を亡くして初めて親に出遇うことが多いと思います。親は子供と一体の関係であり、それは「自利利他」と言う言葉で表すことができます。つまり子供の幸せは親の幸せであるということです。仏様はすべての人々に「あなたが幸せを得なければ、私は幸せになることはない」という存在です。
お経には「若不生者 不取正覚」という言葉があります。「もしあなたがお浄土に生まれなければ、私は覚りを得ません」という意味です。親の願い、仏さまの願いに私たちが目覚めさせていただくということは大きな意味があります。
西川和榮さんの詩に「吸うて吐き 吸うて吐きつるこの呼吸の ただごとでなき このただのこと」というものがあります。目には見えない大切な空気のはたらきによって私たちは生かされています。仏さまは色々なかたちをもって私たちにはたらいています。空気もまた仏さまの姿の一つです。決して当たり前のことではなく、仏さまのはたらきによってここにおらせていただいています。
先日、お寺で法事を勤めました。施主さんの養父の五十回忌と養母の二十三回忌です。施主さんは幼いときに養子に入りました。施主さんの実父は大阪に養子に出したくなかったそうです。その実父の思いが施主さんに伝わって、大阪で頑張られていると思います。その方はお内仏も大事にされており、親からの思いを受け継いでおられる方です。お念仏は私たちを含む広い十方世界に対して呼び掛けられている名前です。ですので、お念仏を「御名」とか「名号」と言います。これは「如来回向」といって、如来様から私たちに対して回し向けて下さっている名前です。これによって如来様のお心を私たちがいただくことができます。曽我量深師は私たちが無条件で絶対的に如来様から信じられていることを「絶対信」と呼びました。お経のなかには「一一の光明 遍く十方世界を照らす 念仏の衆生を摂取して捨てたまわず」とあります。阿弥陀様のはたらきは光となって私たちを照らします。念仏の衆生を摂め取って捨てません。念仏を称える人だけという意味ではなく、あらゆる人に念仏を称えてほしいという意味です。また『浄土和讃』には
十方微塵世界の 念仏の衆生をみそなわし
摂取してすてざれば 阿弥陀となづけたてまつる
とあります。「摂」とは逃げるものを捕まえてでもという意味があります。阿弥陀様が様々な形をとって私を捕まえて助けてくださるということです。「不捨」(捨てない)とは「待つことのできるはたらき」です。『浄土和讃』に
弥陀成仏のこのかたは いまに十劫をへたまえり
法身の光輪きわもなく 世の盲冥をてらすなり
がありますが、これは「阿弥陀様が仏様になられてから十劫(とても長い時間)が経ちました。仏様のはたらきが光となって私たちの闇を照らして下さっています」ということですが、これが「不捨」です。東井義雄先生は「根を養えば 樹は育つ」とおっしゃいました。深い愛情を注いで、大事に育てれば時間はかかるかもしれないがいつかは大きく育ちます。阿弥陀様の「不捨」とはこれと同様、「いつまでも待ってますよ」というはたらきです。阿弥陀様は何を以てしても間に合わないときは私のところに帰って来ると思っておられ、その時まで待っておられます。私たちは生老病死から逃れることはできません。念仏の教えは生と死は一体であり、「生死一如」といいます。これに対して娑婆世界のとらえ方は「生死の境」を作ってしまう世界です。生と死を分けています。無量寿のいのちをもつ阿弥陀仏によって生かされ、浄土に還って仏にならせていただくのです。私たちもまた無量寿のいのちに遇わせていただく身です。
生き死には 花の咲くごと 散るがごと 弥陀のいのちの かぎろいの中(藤原正遠)
神戸で納骨堂・永代供養をお探しの方は→こちらへ