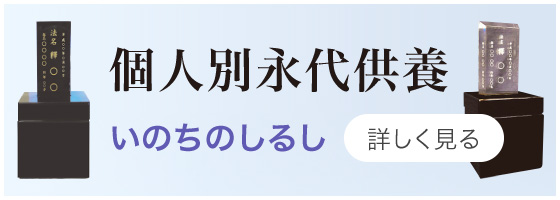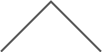今年も暮れてきましたが、改めて齢を重ねるごとにつらい別れが増えてくる気がします。お釈迦様は人生は苦の連続であることを教えて下さいました。「愛別離苦」は仏教でいう「四苦八苦」の五番目の苦しみです。愛しいものとも別れていかなければならないといおう苦しみです。私も両親や友人との別れを経験しています。最近、近くのお寺の住職であった友人が亡くなりました。病の中で彼が言っていた「お互いのお寺でお勤めしあうことが、こんなに嬉しいことだとは思わなかった」という言葉を忘れることができません。彼の院号は「大行院」です。「大行」とはお念仏のことです。お念仏は仏様が呼びかけ続ける大きなはたらきです。私たちは大切だと思っていることでも、それに慣れてくると次第に疎かになってきます。「行」も同様に、私の行であれば疎かになってきます。しかし念仏は仏様の「行」ですので、このようなことはありません。仏の行は「常」に行われている大行です。私たちの行は「恒」、つまり「ときどき」仏様からの常なるはたらきかけによって行われるものです。親鸞聖人はこのように仏の行と私たちの行を区別されました。仏様の常なるはたらきかけがあることによって、私たちは安心してときどき念仏を称えることができます。そこに「他力」のはたらきがあると思います。
本山の報恩講は11月21日から28日まで行われますが、これは親鸞聖人が最後に床に臥せられてから亡くなるまでの期間です。その親鸞聖人にとって一番大変であった期間が我々真宗門徒にとって最も大切な報恩講の期間になっています。『御伝鈔』には亡くなられるときに「念仏の息たえましましおわりぬ。」と記してあります。「念仏の息」とは私たちが生きている限り、仏様がはたらきかけ続けているということです。このことが他力であり、「信心」とはそのことに気付くことではないかと思います。
世自在王仏が出て来られる以前、53の仏様がおられました。法蔵菩薩が世自在王仏と出会い、長い期間の思惟とご修行を経て阿弥陀仏となられ、南無阿弥陀仏の念仏を私たちに届けてくれました。阿弥陀仏が出て来られる背景として世自在王仏の前に53の仏様がおられます。背景ということですが、たくさんの方がお寺とご縁を結んでおられますが、そのご縁を結ぶこととなった背景には大切な方を亡くしたという「悲」の逆縁、つまり「愛別離苦」があることが多いと思います。色々な表情の私たちの今、「果」には悲という「因」があるように思います。私たちが南無阿弥陀に出会う背景が53の仏の歴史として説かれているのだと思います。私も両親や友との果としての「悲」しい別れを通して、たくさんの気付き、「因」をいただくことができました。53仏の二番目は光遠仏ですが、宮城先生は「遠ければ遠いほどその光を増すものを光遠仏というのだ」とおっしゃられました。亡くなられたことによって遠くなったからこそ出会わさせていただくことのできるものの象徴として「光遠」を受け取っています。
子どもは親に対してひどい言葉を浴びせることがありますが、それは親に甘えるが故です。しかし、親が生きている間にそのことに気付くことはないでしょう。正親含英先生は「親に三種の親あり」とおっしゃていました。一つめは戸籍上の親で、私をこの世に産み出してくれた親です。二つめは育ての親で毎日の生活を共にする親です。その親は百面相の親と呼ばれます。これはこちら側の想いによって百のあるが如く変化する親です。こちらの都合によって姿を表す親です。親が生きてる間はこちらの都合に合わせて変化するので、本当の意味での出会いはないのでしょう。三つめは自分が苦しいときに「お父さん」「お母さん」という呼び声としてはたらきかけてくる親です。つらいときでも調子のいいときでも見守り続けてくれる親です。曽我量深先生は念仏のことを「念念仏」とおっしゃられました。「わたしのことを念じてくれる仏を念ずる」という意味です。どんな時でもわたしのことを念じてくれる、それが三つめの親との出会いでしょう。悲しいかな生きてる間にこの出会いを果たすのは難しい。親との本当の意味での出会いは亡くなった後になるのではないかなと思います。「遠ければ遠いほどその光を増す」光遠仏という言葉が胸に響きます。両親や友との悲しい別れを通して、光遠仏という言葉に改めて出遇わせていただいたのではないかと思います。